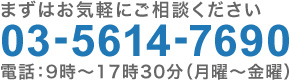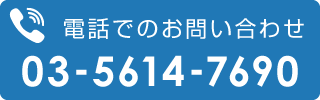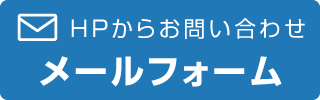証拠能力とは
刑事裁判では,法廷外の供述は原則として証拠能力がありません。
これを伝聞法則といいます。ある事実があったかなかったかを裁判所が判断する際,例えば,警察官が目撃者から事情を聴取し,「犯人の男が右手で刺していた」と話したとします。警察官は,それを供述調書という形にまとめます。
裁判では,検察官がその目撃者の供述調書を証拠として請求します。
このような法廷以外の場所でなされた供述は,弁護人が証拠とすることに同意しない限り,証拠とすることができません。
その目撃者の人が本当に見たのか、見間違いはないのかは,書面からはわかりません。直接裁判所がその人から話を聞かなければ真偽を確認出来ないからです。その結果証人尋問を行うことになります。
以上が原則ですが,このような伝聞法則には例外規定がいくつかあります。
そのうちの1つが321条4項で定められています。
伝聞例外
刑事訴訟法321条4項
鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。
前項には,「その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第1項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。」と規定されています。
従って,鑑定人が作成した鑑定書については,証人尋問において,その鑑定書を自分が正確に作成したことを証言すれば,弁護人の同意がなくても証拠として採用できるのです。
鑑定とは,DNA型鑑定とか法医学者による司法解剖,精神科医による精神鑑定などのように,専門家が作成する書類であり,(その内容が信用できるかどうかは別として)少なくとも鑑定人の鑑定経過が誤りなく記載されていると考えられているからです。
刑事裁判でも,検察官や弁護人が,鑑定書について321条4項により請求しますと法廷で言うことがありますが,以上のような刑事訴訟法の規定に基づいているのです。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。