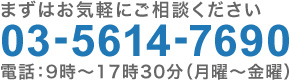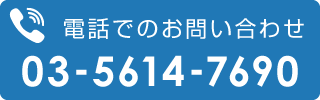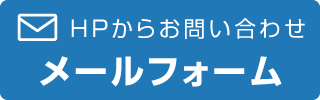刑事弁護コラム
裁判員裁判は私選弁護人を依頼すべきか
裁判員裁判対象事件で逮捕,起訴されてしまった場合に国選弁護人にするかそれとも私選弁護人を選任すべきでしょうか。
裁判員裁判は一定の重大な罪が対象とされており,有罪の場合に科される刑も重くなります。
弁護人の活動が結論に与える影響も大きいため,慎重な検討が必要です。
裁判員裁判の国選弁護人
裁判員裁判は,起訴されると必要的に公判前整理手続に付され,集中して審理が行われるため弁護人の負担が大きくなります。
そこで,現在は原則として2名の国選弁護人が選任されています(一部の事件では捜査段階は1名の場合がありますが,起訴後は2名が原則です)。
国選弁護人の選ばれ方は,各都道府県にある弁護士会に所属する弁護士による国選名簿から配点されることになり,特定の弁護士を国選に選任することを求めることはできません。
そのため,どのような弁護人が国選弁護人として選任されるかは運となります。
地域にもよるのですが,裁判員裁判は重大事件であることから各弁護士会が名簿に登載される弁護士向けの研修を義務づけたり,刑事事件に熱心な弁護士も多く登録しています。
国選弁護だから手を抜くということはなく,弁護士から見ても一線級の弁護士が国選として選任されることもあるでしょう。
また,国選か私選かを検討する際には費用の面も欠かせません。
国選の場合は被告人自身が負担させられることは資力が相応にあって,執行猶予判決となる場合など例外的な場合で,多くは国が負担します。
2名分の弁護士費用だけではありません。
刑事裁判では,捜査機関が収集した証拠の開示を受けて弁護活動をするのですが,その証拠は検察庁に対して謄写(コピー)を求める必要があります。その謄写費用は1枚30円以上(地域によります)かかります。この謄写費用も国が支払います。
裁判員裁判の謄写費用は,時に数十万から100万以上になることもあり,私選弁護人を選任するときには,この謄写費用も負担しなければなりません。
裁判員裁判での私選弁護人
私選弁護人を頼むメリットはどこにあるでしょうか。
それはやはり,裁判員裁判において弁護人の力量が大きく左右するという点に挙げられます。
裁判員裁判は,公判前整理手続に付されます。そこでは検察官に証拠の開示を求めたり,あるいはこちらの証拠を裁判所に採用させる必要があり,刑事事件に熟達しているか否かで大きく変わってきます。
また,法廷での弁護活動,証人尋問や,冒頭陳述,弁論などといった法廷技術は,裁判官,裁判員を説得する上でとても重要な技術ですが,このような法廷技術は,訓練なくして身につくものではありません。
裁判員裁判の国選弁護の名簿には刑事弁護を得意とする弁護士もいれば,経験に乏しかったり,あるいはそこまで熱心ではない,裁判員裁判の研修を積極的に受講していないというような弁護士がいるのも事実です。
そして,国選弁護人は,自分で選ぶことができず,かつ,信頼が十分に出来ない場合でも,交代を求めることができません。
特に否認事件では私選弁護のメリットはより大きなものとなるでしょう。
他方で,私選弁護人は費用がかかります。裁判員裁判は公判前整理手続期間を含めて,半年から2年以上かかることも珍しくありません。
公判は集中的に行われるため,弁護士もその事件に集中するため,どうしても弁護士費用は高額となります。
事件によりますが2名選任するとして,謄写費用含め数百万かかると見ておく必要があります。
国選か私選か
国選でも熱心かつ熟達した刑事弁護人の場合もありますから,選任された国選弁護人が信頼できるなら任せるということでもよいかもしれません。
私選弁護人はいつでも選任できます(私選が選任された時点で原則として国選は解任になります)。
ただし,私選弁護人としての活動は早ければ早いほうがいいです。
迷われるようでしたら,とりあえず刑事事件を中心に扱っている弁護士に相談してみることとお勧めします。
ただし,一審は国選でやってみて,うまくいかなかったら控訴審は私選を選任しようというのはお勧めしません。
日本は三審制をとり,地裁,高裁,最高裁,とありますが,市民も参加して地裁で行われた裁判員裁判の結果を,高裁の裁判官が控訴審で破棄して判決を変更することはよほどの事情がない限りありません。
まずは第1審に全ての力を注ぐ必要があります。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
第一回公判期日前の証人尋問の注意点
第一回公判期日前の証人尋問とは
公判期日に行われる証拠調べとして、証人尋問が行われます。被告人も出頭し、公開の法廷で証人に対し検察官や弁護人が尋問します。
ところが刑事訴訟法は、第一回公判期日より前に、つまり公判手続が始まる前に、証人尋問を行うことを認めています。刑事訴訟法226条、227条が定める、第一回公判期日前の証人尋問がこれです。
226条は、犯罪の捜査に欠くことができない知識を有すると明らかに認められる者が、捜査機関による取調べを拒んだ場合に証人尋問ができるとします。227条は、取調べでは任意に供述した(つまり取調べに応じて話をしていた)者が、公判期日では前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができない場合に、証人尋問ができるとします。
実務上特に問題になることが多いのが、227条のケースです。例えば被害者や重要な証言をすることが期待されている共犯者が、公判廷での証言を拒んだり、出廷しないことを予め明言している場合なども該当すると判断されることがあります。
この第一回公判期日前の証人尋問は、非公開の法廷で行われます。そして、被告人と弁護人の立会権がありません。刑事訴訟法は、「捜査に支障を生ずる虞(おそれ)がないと認めるとき」は、被告人、被疑者、弁護人を「立ち会わせることができる」としています。つまり裁判所の裁量次第で、立会が認められないこともあります。弁護人のみの立会が認められ、被告人本人が立ち会えないということも珍しくありません。立会を許された弁護人は、通常の公判廷での尋問と同様に、証人に対して反対尋問を行うことができます。ただし、証人尋問調書を謄写できない等の違いがあります。
弁護活動の留意点
被告人不在の場で、しかも十分な証拠の開示を受けられない段階で証人尋問を行うことは、証人の一方的な証言を許す機会にもなりかねず、被告人にとって極めて大きな不利益を招きます。事案にもよりますが、弁護人としては上記の証人尋問を満たす要件が認められるかについて厳しく精査し、反対意見を積極的にのべるべきです。もっとも、検察官の意見書や請求書を謄写することもできず、的確な反論が難しいケースも少なくありません。
第一回公判期日前に証人尋問が実施されることとなった場合は、同尋問での証言が、公判調書という形式で、その後の公判で証拠採用されることを見越して、尋問をする必要があります。尋問調書を読むだけで、裁判官、裁判員が、弁護人の尋問の意味や証人の信用性をなるべく的確に判断できるよう、質問の内容や訊き方に配慮する必要があります。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
介護殺人の難しさ
介護の末に要介護者を殺害してしまった,として刑事事件に問われることは少なくありません。
心身の障害に苦しみ,自ら殺害を依頼するケースもあれば(嘱託殺人罪),介護者が限界に達して依頼なく殺害してしまうケースもあります(通常の殺人罪)。
ただし,介護殺人と一口にいっても,介護の程度や期間,事件の動機などによって様々です。
生活に苦しむ要介護者を楽にしてあげたい,という動機なのか,単に介護を負担に思い自分が遊びたいという動機なのか。
周囲への助けを求めたか,利用できるサービス等があったかなども量刑に影響します。
また,介護者自身がうつ病等患っているケースも珍しくありません。
このように介護殺人にも様々な事情があり,量刑もかなり幅が広くなります。
下は殺人既遂でも執行猶予が付くこともあれば,懲役10年を超えることもあります。
弁護活動にあたっても,長年の介護の実態をできる限り把握する必要があり,大変な事件類型の1つです。
なにより,本人自身が,自責の念に駆られている場合も多く,あるいは,心中を企図したケースなどでは,自殺念慮が続いている人もいます。
弁護人は,本人に寄り添いながら,本人が尽くしてきた介護の実態を伝え,その苦しみを裁判官,裁判員に理解してもらう必要があるのです。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
通常刑事裁判 第1回公判に向けて弁護の裁判準備
裁判員裁判でない通常の刑事裁判は,起訴がなされてから1,2か月ほどで第1回公判が行われるのが通常です。
第1回公判では,起訴状が読み上げられ,裁判官から被告人,弁護人に対してそれぞれ,起訴状の内容に間違いがあるか意見を聞かれます。
その後,検察官が証拠によって証明しようとする事実について述べる冒頭陳述を行い,証拠の取調べを請求します。 (さらに…)

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
尋問する証人と会うことの重要性
証人尋問は準備が重要
刑事事件の裁判では,証人の尋問がよく行われます。
証人の尋問では,検察官や弁護士が,法廷で証人に質問をして,事件について答えてもらいます。そして,証人が話したことが,そのまま証拠となります。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
法務・検察行政刷新会議
法務・検察行政刷新会議
カルロス・ゴーン氏の海外逃亡及び黒川元検事長の勤務延長問題を契機として、法務省内に法務・検察行政刷新会議が設置され、令和2年12月24日で会議を閉会しました。 (さらに…)

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
保釈中の旅行について
保釈の条件
保釈が許可される場合、ほとんどのケースで「海外旅行又は3日以上の旅行をする場合には、前もって、裁判所に申し出て、許可を受けなければならない」といった、旅行に関する指定条件が付されます。 (さらに…)

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
供述の迫真性,具体性の危険性
迫真的な供述は信用できるか
刑事裁判で事実が争われると,証人尋問や被告人質問が行われます。 (さらに…)

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
捜査段階における証拠把握
捜査機関による証拠収集
捜査段階において,勾留といった身体拘束がなされるかどうかや,起訴されて刑事裁判を受けることになるかどうかは,警察,検察が収集した証拠に基づいて判断されます。
身体拘束がなされないようにするため,起訴されないように活動するためには,弁護人において,警察,検察が収集している証拠内容を把握することが重要といえます。
しかし,捜査段階において,警察,検察が収集した証拠を弁護人が直接閲覧したりして確認することはできません。 (さらに…)

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
弁護人による控訴申立と取り下げ
第1審の判決が有罪判決で不服がある場合,被告人は判決の翌日から14日以内に控訴申立をすることができます。 (さらに…)

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。