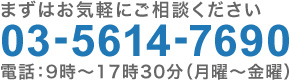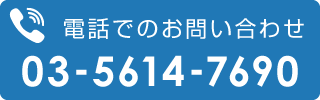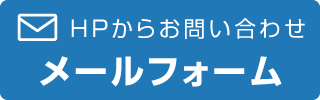Author Archive
控訴趣意書の作成
1 刑事裁判における控訴審
第1審の判決に不服がある場合には,控訴申立をすることができます。 (さらに…)

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
在宅事件での取調べ対応
捜査機関の捜査は、逮捕されて「身柄拘束された状態」で進められるイメージも強く、そういった事件も多数存在します。
ですが、事件によっては、身柄拘束をせず、「在宅」のまま捜査が進められることも多いです。また、最初は逮捕されていたけれど、処分保留釈放となって、在宅に切り替わる事件もあります。このような在宅の事件でこそ、幅広い防御活動が重要になります。
今回は、在宅事件で行われる任意取調べでの防御活動を紹介します。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
逮捕後に国選弁護人がつくまでの手続き
逮捕された後,すぐに国選の弁護人がつくというわけではありません。
逮捕後に国選の弁護人がつくのがいつからかは,現在の制度では「勾留状が発せられている場合」(刑事訴訟法37条の2第1項)とされています。
逮捕の後,さらに勾留という10日間の身体拘束が続くことになって初めて国選の弁護人として弁護士がつくことになるのが現在の制度です。
警察による弁解録取
国選の弁護人がつく前までの逮捕された被疑者に対する手続きとして,まず,警察による弁解録取が行われます。
逮捕された犯罪事実について被疑者に弁解の機会を与えるという手続きです。
この時,被疑者が弁解した内容について,弁解録取書という書類が作成されます。
実質的に犯罪事実についての取り調べが行われ,供述調書が作成されることになります。
弁解録取だけで警察の取り調べが終わるわけではありません。
弁解録取書を作成した後も,さらに犯罪事実,事件に至る経緯,事件後の出来事等について詳しく取り調べが行われ,供述調書が作成されます。
自身の経歴,職歴,前科前歴,家族関係,生活状況等の身上関係といわれる事柄についても取り調べが行われ,供述調書が作成されます。
検察官送致・検察による弁解録取
警察がさらに身体拘束を続けて取り調べ等の捜査を行う必要があると考える場合,手続きとしては,逮捕から2日以内に検察官に送致する送検という手続きを行います。
送検を受けた検察官からも,被疑者に対して弁解録取が行われます。
逮捕された犯罪事実についての被疑者の弁解を聞くというだけに止まらず,検察官からも詳しく取り調べが行われて供述調書が作成されることが多いといえます。
勾留請求・勾留質問
検察官がさらに身体拘束を続けて取り調べ等の捜査を行う必要があると考える場合,手続きとしては,送検から1日以内に裁判官に勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判官は,被疑者に対して勾留質問を行います。
警察,検察官と同様に,被疑者に対して犯罪事実に関する陳述を聴くという手続きであり,勾留質問において被疑者が供述した内容は勾留質問調書という書類に記録されます。
裁判官が勾留を認める場合,検察官が勾留請求した日から10日間の身体拘束が続くことになります。
この10日間の勾留はさらに最大10日間延長されて取り調べ等の捜査を受ける可能性があります。
逮捕後すぐに弁護士の助言等を受けることが重要
こうした手続きのため,逮捕された後に国選の弁護人がつくことになるまで,逮捕から2~4日程かかることになります。
また,国選の弁護人がついたときには,既に勾留されていてさらに10日間の身体拘束が続くことになっていることになります。
また,国選の弁護人がつくことになるまでに,既に,警察,検察の取り調べは始まっていて供述調書が作成され,裁判官の勾留質問も終わって勾留質問調書が作成された後ということになります。
身体拘束を受ける日数という点でも,取調べ等の捜査を受けるという点でも,現在の国選弁護人の制度は十分とはいえません。
国選の弁護人がつくのを待つというのではなく,逮捕後すぐに弁護士の助言を受け,弁護士が弁護活動を行うことが重要といえます。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
強盗致傷事件について
1 強盗致傷罪は裁判員裁判対象事件
強盗致傷罪とは,強盗という犯罪を起こし,かつ被害者や関係者に傷害を負わせた場合に成立する犯罪です。 (さらに…)

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
警察・検察の取り調べを予想する
逮捕されるとすぐに警察,検察の取り調べを受けることになります。
取り調べで話した内容は供述調書を作成されたり録音録画されたりし,起訴・不起訴や裁判での有罪・無罪と刑の重さを決める証拠になります。
取り調べに適切に対応するためには,警察,検察がどのような取り調べを行うのか予想することが重要です。
警察,検察がどのような取り調べを行うか
警察,検察は,犯罪事実や犯人を証明することを考えて取り調べを行うものといえます。
警察,検察がどのような取り調べを行うか的確に予想するためには,このような犯罪事実や犯人であること証明するためにどういった事実が問題となるかを具体的に検討できることが重要です。
そのためには,法律や裁判例などの前提知識が必要であり,その上で事案や証拠内容を十分に把握することが必要です。
法律や刑事裁判になじみのないご本人が自分で判断するのは困難で,弁護士の判断に従うことが重要です。
例えば,騙されて詐欺行為に荷担することになり逮捕されたという事案であったとします。
ご本人としては自分も騙されたので無罪であると考えるのは当然です。
しかし,騙されたとしても犯罪が私立する可能性があります。
刑事裁判において犯罪が成立するためのご本人の認識としては,犯罪である可能性を認識しながらもあえて行ったという程度のもので,犯罪が成立しうるものです。
警察,検察の取り調べとして,ご本人が自分も騙されたと説明したとしても,それで捜査は終わりとなり釈放され不起訴になるということは全く期待できません。
本件以前の出来事や荷担することになった経緯,関係者とのやりとりなどについても取り調べられることが予想されます。
こうした事柄について,記憶が不確かであったり不正確であったりするにもかかわらず,警察,検察の取り調べで供述した内容が証拠となることで,有罪となってしまう危険性があります。
供述させようとして予想される取り調べ
こうした警察,検察の取り調べに対しては,黙秘権を行使することが考えられます。
しかし,ご本人が黙秘権を行使すると言ったとしても,警察,検察が取り調べを終了するということは全く期待できません。
ご本人が黙秘権を行使すると言っても取り調べは続きます。
むしろ,ご本人の意思に反して供述させようとする取り調べが行われることが予想されます。
取り調べに応じないことを強く非難するような取り調べを行うことや,逆に供述しないことがご本人の不利になるとするような不安にさせる取り調べを行うことなどが予想されます。
あるいは,取調べにおいて事件とは関係のない雑談をすることで,事件についての話をすることの取り調べについても話をさせようとすることなども予想されます。
こうした取り調べに対してどのように対応すべきかは,ご本人自身が判断することは困難です。
取り調べ自体に対してどのように応じるかについても,弁護士の助言を受けてその判断に従うことが重要です。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
証拠の入手方法
1 刑事裁判のための証拠収集
刑事裁判は,法廷に提出された証拠によって有罪,無罪,あるいは有罪であれば量刑が決せられます。
証拠には,被害者や関係者などの証人,書証,物証があります。
刑事裁判で自らの主張を裏付け,あるいは検察側の主張を弾劾するための証拠の入手方法にはどのようなものがあるでしょうか。
2 証拠の開示
まず証拠を入手する基本となるのが検察官に対する証拠の開示請求です。
捜査機関は,警察,検察が,たくさんの捜査員を投入して関係者から話を聞いたり,証拠を押収します。また捜査機関ないし外部機関に委託して鑑定や実験なども行います。
それらの証拠は当然には弁護側には開示されません。
裁判では,検察官が自らの主張を立証するために必要だと考える証拠だけが請求され,それは弁護人にも開示されますが,検察官が必要ではないと判断したものは,開示されないため,弁護側から検察官に証拠の開示請求をする必要があるのです。多くのえん罪事件で,被告人側に有利な証拠が開示されなかったことが要因となっているように,きちんとした証拠の開示が何より重要なのです。
3 新たな証拠の収集法方
証拠の開示は,起訴された段階ですでに捜査機関によって収集された証拠の開示を求めるものです。
捜査機関が入手していない証拠の入手方法には,いくつかの方法が考えられます。
大きくわけて,① 捜査機関に入手させる ② 裁判所を通じて入手する ③ 弁護人自ら入手する ことが考えられます。
①,②の捜査機関や裁判所を通じて入手する場合には,当然その内容を検察官(場合によって裁判所)が把握することになります。
内容によっては,捜査機関,裁判所に知られる前に弁護側で把握して検討したいという場合もあるでしょう。
そのため,まずは③の弁護人が独自に入手することを検討します。
4 弁護人による証拠収集
弁護人による証拠収集は,例えば弁護人自身が関係者に話を聞いたり,現場に行ったり,各種機関に鑑定や実験を依頼することはできます。
問題は,相手が提出や聴き取りを拒んだときに,強制的に入手する方法がない,という点です。
弁護士には,弁護士法23条による弁護士会照会という制度があり,一定の場合には有効ですが,企業による情報管理の点から,開示されない場合も珍しくありません。
5 捜査機関,裁判所に入手させる
強制力によって入手するしかない場合,捜査機関や裁判所を通じて入手するしかありません。
捜査機関は,捜査事項照会という関係機関に対して照会をして回答を得るということを良く行っていますし,必要があれば,裁判所に捜索差押え令状を請求して,強制的に押収することも可能です。
捜査機関はもちろん弁護人の要求に応じる義務はないので,捜査機関に~のような証拠が必要だから収集して欲しい,という申し入れを行い,捜査機関の判断で収集することになります。
場合によって,公判前整理手続などで裁判官を交えて証拠の必要性を議論し,裁判官から促してもらうということもあります。
また,裁判所を通じた入手には,裁判所に対して,公務所等照会をしたり裁判所自身に差押え,提出命令等の申立をすることが可能です。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
裁判員裁判における量刑の判断
裁判員裁判は,一定の重大犯罪が対象となっています。
殺人,傷害致死,強盗殺人,強盗致死,強盗致傷,現住建造物等放火,強制性交等致傷などの罪です。
一般の市民から選ばれた裁判員が裁判官とともに有罪無罪の判断の他,有罪とする場合は言い渡す刑の重さも判断します。 (さらに…)

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
控訴や上告をすべきか
日本の刑事裁判
逮捕され起訴されると刑事事件の第1審が地方裁判所で行われることになります(一部の軽微な事件は簡易裁判所の場合もあります)。
第1審の裁判に不服があり控訴を申し立てると,事件は高等裁判所で第二審として審理されます。
控訴審の判決にも不服があり,上告を申し立てると最高裁で第三審審理されることになります。
このように,日本の刑事裁判は三審制を採用しています。
しかし,地裁,高裁,最高裁の審理は違う裁判官が判断するものの,その審理の内容は全く異なります。
裁判員制度の導入もあり,日本の刑事裁判における第1審重視の傾向は強まっており,控訴審での破棄率は10%前後で,上告審で破棄されるのは年数件というレベルです。
控訴すべきか
控訴すべきかどうかを考えるときには,
① 保釈されているか,されていなければ未決の日数
② 控訴審での見通し
を検討する必要があります。
前提として,控訴審は,原判決の言い渡し日から概ね1ヶ月半~2ヶ月後くらいで控訴趣意書をの期限が定まります。
控訴趣意書とは,第1審判決に対する不服な点を記載した書面です(通常は弁護人が作成します)。
控訴趣意書を提出して,そこから1ヶ月程度で第1回公判,さらに2週間~1ヶ月で判決期日というのが一般的な流れです。
そのため,控訴審の審理期間は概ね3ヶ月半~5ヶ月くらいで終了することがほとんどです。
拘束されている場合の未決勾留日数は約2ヶ月を超える部分が算入されることが多く,裏を返せば2ヶ月は無駄に拘束されるということになります。
第1審で言い渡された刑期が比較的短期である場合,控訴してダメだった場合は,社会復帰が2ヶ月遅れるということを意味しますので,その点を検討する必要があります。
また,控訴して拘束されている場合,地裁の管轄地の拘置所から東京,大阪,名古屋などの高裁所在地の拘置所に移送になります。
控訴審の見通し
控訴するかどうかという点において,最も重要な点は控訴して第1審が見直されるかどうかです。
確率的に言えば,10%なので可能性が高いとは言えません。
特に犯罪事実に争いはなく量刑が問題となる事案においては,量刑というものにはある程度の幅があり,高裁の裁判官から見て仮に若干重いなと思えても,同種事案などと比較して適正な幅の中に量刑が収まっているような場合には破棄されないことがほとんどです。
第1審判決が量刑の基礎とした事実自体に誤りがあるとか,第1審判決後に新たに示談が成立したなどの事情がないと,単に第1審判決の評価が不当で重すぎるといったことでは控訴審で見直される可能性は少ないといえます。
事実を争う否認事件の場合を考えてみると,控訴審の基本的性格が,第1審判決の当否を審査するものとされており,証拠調べをやり直すものではありません。
新しい証拠を取調べることには消極で,第1審の証拠から第1審の判決が正しいのかどうかが審査されることになります。
従って,控訴審の見通しを考える上では,第1審の証拠から認定した第1審の判断それ自体に,論理的,あるいは常識的に考えて不当な点があるといえなければならないのです。
上告すべきか
最高裁に上告すべきかどうか,という点についてです。
最高裁での上告審の審理期間は概ね控訴審と同じで,3ヶ月~5ヶ月であることが多いです。
ただし,未決は約4ヶ月を超える部分が算入される運用で,概ね4ヶ月で終了することから,未決が算入されない(4ヶ月社会復帰が遅れる)ということがほとんどです。
また,上告審では原則裁判自体が開かれず書面審理であることから,被告人は高裁所在地の拘置所から移送にはなりません。
そして,何より圧倒的に破棄される(見直される)ことがないという実情です。
刑期にもよりますが,上告するかどうかは十分慎重に検討しなくてはならないでしょう。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
接見等禁止を解除する
弁護士以外と面会できない
身体拘束をされている人にとって、家族と面会できる時間というのは、精神的にも大事な時間になります。時には、手紙のやりとりも、心の支えになると思います。
また、衣類や書籍を始めとして、家族から身体拘束されている人に対して、差入れすることも、重要です。
ですが、事件によっては、裁判所から「接見等禁止命令」といって、弁護人以外との面会や、物・手紙のやりとりが禁止される場合があります。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
公判で自首はどう扱われるか
自首とは何か
刑法は自首について「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」とされています(刑法第42条1項)。
減軽がされた場合、有期の懲役刑ですと、法律上言い渡される刑の上限(長期)及び下限が半分になります。例えば強制わいせつは「6月以上10年以下の懲役に処する」とされていますが、路上で強制わいせつをした後、我に返って反省して近くの交番に駆け込み、自首が成立したとして、減軽が認められると、「3月以上5年以下の懲役」が刑の選択の範囲となります。また、宣告できる刑の幅が変わるだけでなく、実際に宣告される刑が軽くなる傾向にあります。つまり自首したことが有利な情状とされ、刑を軽くする事情として扱われます。
どのような点が争われるか
自首が成立するためには様々な要件があります。刑法の教科書でもそれなりに頁をさいて解説されるような論点ですし、相当数の判例が蓄積されていますが、まず問題になりやすいのは「発覚する前」に自首したといえるかどうかです。犯罪事実とその犯人が捜査機関に判明している前に、犯人が、自分がした犯罪事実の存在や内容を捜査機関に告げる必要があります。
ですから、例えば先程の例で、事件後1時間たって犯人が最寄りの警察署に出頭し、さきほど路上で女性を襲ってしまった、と申告したとします。事件の3分後に被害女性が110番通報していたとすると、この申告の時点で犯罪事実の存在や内容自体は捜査機関に発覚していますが、犯人が誰かがまだ分かっていなかったとしたら、自首が成立し得ます。
他方で、出頭するかどうかを迷っていた結果、2日後になったとします。この時点で、前科の記録や目撃証言をもとに、捜査機関の方では犯人が誰か分かっていた場合、その後に出頭しても自首は成立しません。ですから、事件後時間が経たない間に出頭するのはとても重要です。
裁判では、出頭の時点でどこまで警察が犯罪事実や事件を把握していたか、ということや出頭との先後関係がシビアに争われることもあります。必要であれば、捜査を担当していた警察官を尋問し、出頭の時点で判明していた事実の内容を明らかにしなければならないこともあります。
また、自発的に行ったかどうかも、争点となることがあります。自首と似て非なるのは、警察官から追求を受けて、罪を認めたようなケースです。ですから先程の例でいうと、事件を起こして逃走を開始した3分後に、犯人がたまたま路上をパトロールしていた警察官から職務質問を受けたとして、その挙動を怪しまれて追求され、観念して「先程路上で女性を襲ってしまいました。」等と認めた場合には、自首は成立しないと言えます。
このように自首が成立するかについては様々な論点があり、自首に関する主張を認めさせるには、深い法律知識や尋問能力等が要求されます。弁護人も自首が成立する事案なのかを仔細に見極める必要があります。
自首での減軽を求める場合の注意点
さらに自首を主張する上で重要なのが、法律が「その刑を減刑することができる」としている点です(刑法第42条1項)。つまり自首が成立するとしても、刑を減軽しない、という判断がなされることもあるのです。さらに情状においても、自首をそこまで大きく評価しない、との判断がなされ、結果的に刑がそこまで軽くならない、ということもあります。
自首で減軽がなされる根拠としては①自首がされれば真相が解明されることから、減軽という恩恵を与えてこれを促進するという政策的な根拠②自ら犯罪事実を告げて、自身を訴追するよう求める点で、向けられている非難が減少する、との2点が挙げられることが多いと言えます。減軽が認められない事案は、この趣旨に反するような行為をしているケースが多い傾向にあります。例えば自首はしているものの、直後に事件に関係のあるラインメッセージを消去して証拠隠滅を図った、というような場合などです。自首をしなくても速やかに犯罪事実や犯人は捜査機関に判明したはずであるから、自首がなされた意味は大きくない、というような主張が検察官からなされることもあります。
弁護人は自首が成立する場合でも安心せず、なぜそれを根拠に刑を軽くしてよいか、丁寧に主張立証する必要があります。特に裁判員裁判では、上記のような自首制度の趣旨を裁判員に分かりやすく説明した上で、政策的な観点からも責任減少の観点からも、軽い刑を言い渡さなければ法の趣旨に反する、との主張を的確に行わなければなりません。
なお、現在の裁判実務では、刑の大枠は犯罪行為自体に関する事情(犯情)に基づいて定められ、自首などのそれ以外の事情は、あくまで調整要素として扱われます。しかし執行猶予が認められるかがシビアに争われる事案などでは、自首の成否やそれに基づく減軽の可否が決め手となることもあります。弁護人はあきらめずに自首に関する主張を尽くし、依頼者のために少しでも軽い結論を求めていかなければなりません。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。