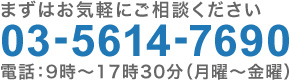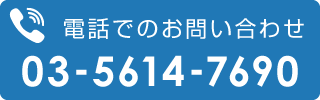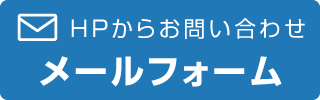Author Archive
強盗致傷罪で逮捕・勾留 早期釈放の弁護活動
強盗致傷罪は裁判員裁判対象事件です。刑法では無期懲役,または6年以上の有期懲役と重い刑が定められています。
強盗致傷罪で逮捕,勾留された事件について,東京ディフェンダー法律事務所の弁護士が弁護人の一人として活動し裁判官の勾留決定に対する準抗告が認められ早期に釈放されました。 (さらに…)

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
久保有希子弁護士が司法研修所の刑事弁護教官に就任
当事務所の久保有希子弁護士が、5月から最高裁判所司法研修所の刑事弁護教官に就任しました。 (さらに…)

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
否認事件と公判前整理手続
否認事件とは
起訴された犯罪について検察官の主張と弁護側で争いがある場合を否認事件といいます。
犯人でない,という無罪主張だけでなく,殺人未遂で起訴されて行為は間違いないものの殺意はなかったから傷害罪であると主張する場合もあります。
また,事実の争いだけではなくて,正当防衛や責任能力の有無という法的評価が争いになることもあります。
このような犯罪の全部又は一部の成立に争いがある場合を否認事件といいます。
これに対し,起訴された犯罪が成立することに争いがなく,主たる裁判のテーマが被告人に科される量刑である場合を量刑事件や自白事件と言ったりします(なお,量刑事件といっても事実に全く争いがないというわけではありません。例えば殺人事件で起訴された場合に,検察官は保険金目的であると主張し弁護側が単なる怨恨であると主張するようなケースです。殺人事件においては動機がなんであるかは刑期を左右する大きな事情であり,事実の争いが大きな意味を持つことも少なくありません)。
公判前整理手続とは
否認事件を公判で闘う場合には,公判前整理手続に付してもらうことが出発点として重要です。
公判前整理手続とは,公判が始まる前にどのような点が争点となるか,どのような証拠調べをするかを整理するための手続です。
重大事件を対象とする裁判員裁判対象事件では,必要的に公判前整理手続が行われることになりますが,裁判員裁判対象外の事件では,基本的に公判前整理手続に付すことを当事者から請求して,裁判所が決定することになります。
刑事訴訟法 316条の2 1項
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
公判前整理手続に付された場合とそうでない場合の違いは,大きく以下の3点です。
① 公判前整理手続で当事者双方は主張を明らかにする必要がある
② 原則として取調べて欲しい証拠は公判前整理手続で請求しなければならない
③ 検察官に対して証拠開示を求めることができ,証拠の一覧表も交付される
公判前整理手続に付すことの重要性
上記の①,②の主張や証拠を公判前整理手続で出し合うという点は,公判前整理手続の大きな特徴です。
そもそも公判前整理手続は,一般市民が裁判員として参加する裁判は集中的に行わなければならないことから,予め判断すべき事項(争点)とそのためにどのような証拠を調べるかを決めておく必要があることから,設けられた制度です。
そのため,
① 検察官が証明予定事実(立証使用とする事実)
② 検察官の証拠調べ請求
③ 弁護人の予定主張(法廷で予定している主張)
④ 弁護人の証拠調べ請求
が行われることになります。
そして,重要なことが,証拠調べ請求は,公判前整理手続終了後はやむを得ない事由がない限り出来ない,という点です。
折角整理して公判をはじめたのに,さらに証拠請求ができるとすれば,裁判をやり直さなければならない事態にもなりかねないからです。
公判前整理手続に付すべき大きな理由の1つが,この証拠制限なのです。
検察官が公判を見てから,補充捜査をしたり,新たな証拠を請求することを封じることができるのです(弁護側も同様です)。
証拠開示の重要性
さらに公判前整理手続に付すべきもう一つの理由が,証拠開示です。
犯罪が疑われた場合,警察,検察は,膨大な捜査員と税金を投入して,証拠を集めます。必要があれば強制的に押収することもできます。
これに対し弁護側は,強制力もマンパワーもなく,国選弁護などでは経済的資力もありません。
もちろん事件の中には,弁護人が苦労の既に証拠を探し出したり,作り出して無罪に繋がるという場合もありますが,多くは,捜査機関が収集した証拠の中に活路を見いだすのです。
しかしながら,検察官は、自らの主張を裏付ける証拠のみを裁判所に請求しますから,弁護側に必要な証拠は当然には手に入れることができず,証拠開示を求めていかなければなりません。
しかも,そもそもどのような証拠を集めたのかすら弁護側には分かりません。
そこで公判前整理手続に付されると,捜査機関が収集した証拠の一覧表というものを交付させることができ,証拠開示の手がかりになるのです。
また,公判前整理手続に付された事件では,類型証拠開示請求や主張関連証拠開示請求という制度が設けられており,検察官との間で証拠開示を巡って対立したときには,裁判所に証拠開示命令を出すよう請求することもできます。
このようなメリットから,否認事件においては公判前整理手続に付すことを求めることが充実した弁護活動のために必要なのです。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
持続化給付金詐欺の捜査弁護
新型コロナ禍において、持続化給付金詐欺が、急速に増えています。ニュースで目に触れる機会も多くなりました。持続化給付金詐欺に関わってしまった人も、数多くいることが予想されます。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
大麻事案の特徴
大麻事案の特徴
大麻取締法の改正が議論されています。現在日本で大麻を所持することは刑罰の対象となりますが、大麻を使用しただけでは罰則はありません。他の代表的な薬物、例えば覚醒剤やコカイン、MDMAなどが、所持についても使用についても罰則の対象となるのとは異なります。
違いはそれだけではありません。大麻の所持事案に関しては、他の薬物所持の事案と比べ、運用上顕著な特徴があり、弁護人もその違いを理解した上で適切な方針選択をする必要があります。
微量であれば不起訴になることがある
薬物所持事案で争いのない場合、日本ではほとんどの事案で公判請求という処分が検察官からなされます。すなわち、検察官が起訴し、正式に公判が開かれ、有罪判決を受けるというのがもっとも多いパターンです。
大麻を所持していたとしても、持っていた量が非常に少なければ、不起訴になることがあります。明確な基準があるわけではありませんが、大麻の1回分の使用量とされている約0.5g(但し、乾燥大麻の場合。大麻樹脂の場合は約0.1g程度。)を下回る所持量の場合には、所持の事実に争いがなく、被疑者本人が認めていたとしても、不起訴処分(起訴猶予)になることがしばしばあります。
起訴猶予処分とは、犯罪事実の認定に問題がないことを前提に、起訴することによる弊害等を考慮して敢えて起訴しない処分です。起訴するか否かの判断においては、検察官に極めて大きな裁量が認められており、上記のような処分傾向の背景にどのような考え方があるのか、正確に知ることは困難ですが、1回使用分にもみたない微量の所持は、違法性が決して高くないことを考慮しているものと推測されます。
もっとも、このような微量な所持事案が起訴猶予となるのは、ほとんどが初犯の場合です。薬物事犯の前科がある場合などでは、微量の大麻所持であっても、起訴されることはよくあります。
他の薬物ではどうでしょうか。覚醒剤の所持の場合ですと、初犯で、かつ所持量が1回分にもみたないような微量であったとしても、所持の事実に争いがないのであれば起訴されることがほとんどです。大麻とは異なります。所持している薬物によって、正反対の結果となりうるのです。
他によくみるケースは、覚醒剤に加えて、少量の大麻を所持しているようなケースでは、覚醒剤の所持のみが起訴され、大麻の所持については起訴されないというものです。覚醒剤の所持について公判が開かれる以上、大麻の所持についてはわざわざ起訴する価値に乏しい、という判断が働いているものと思われます。
他の薬物事案と比べて勾留がされにくい
日本では捜査段階で安易に勾留決定がなされます。勾留とは、最大20日間に及ぶ、起訴前の身体拘束です。軽微な事案であっても、必要性の乏しい勾留が日常的になされているのが現状です。特に薬物事犯では、売人等の背後に組織的な背景が存在すると考えられること等から、ほとんどの事案で勾留がなされる一方、在宅のまま捜査がなされる場合は例外にとどまってきました。
しかし、大麻所持の事案については、以前と比べて勾留請求が却下される事案が増えてきています。仮に勾留がついたとしても、勾留延長請求が却下され、勾留から10日目で釈放され、在宅捜査に切り替えられるという事案も相当増加しているように思えます。奇妙なことに、これも大麻所持事案特有の傾向で、例えば覚醒剤やコカインの所持の事案では、(例外はあるとしても)依然として漫然と20日間の勾留がなされる事案が圧倒的に多数です。
そもそも単純な薬物所持事案であれば、証拠関係も極めてシンプルです。現行犯逮捕事案であれば、所持品検査等により所持の態様は明らかとなっていますし、犯罪事実の存在も明白です。自分一人で使うために持っていた、というようなケースでは、関係者との口裏合わせ等の罪証隠滅がなされる可能性も乏しく、勾留の要件も必要性も満たされない場合が多いと言えます。つまり大麻の単純所持の事案で勾留がなされないのは、法律上の要件からも至極当然だといえるケースが多いと思われますし、他の薬物、例えば覚醒剤の所持事案でも同様のはずです。勾留の判断においては、大麻のみを特別扱いする理由は見出し難いのです。
今後、勾留に関する運用は変わり得ます。他の薬物の所持事案についても、安易な勾留は抑制されるようになるかもしれません。いずれにせよ弁護人は、最先端の運用や相場観を踏まえつつも、諦めずに粘り強く不当な勾留を回避するための働きかけを行っていくべきです。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
逮捕・勾留された 早期の釈放を目指す弁護活動
犯罪を犯したことを疑われて逮捕された後,さらに勾留という身体拘束を受けて取調べなどの捜査を受ける可能性があります。 (さらに…)

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
強盗殺人と強盗致死
強盗殺人と強盗致死の法定刑
強盗殺人とは,強盗をした犯人が人を殺害した場合です(必ずしも殺害相手は強盗の被害者に限られません。目撃した人を殺害した場合などを含みます)。
殺害に故意がある(殺意がある)場合が強盗殺人であり,殺意がないけれども暴行の結果人を死なせた場合が強盗致死になります。
刑法第240条は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と規定しています(前段は怪我をさせた場合で強盗傷人又は強盗致傷罪です)。
つまり,法定刑では,強盗殺人も強盗致死もいずれも「死刑又は無期懲役」のみが定められています。
ちなみに普通の殺人罪は「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」(刑法199条)であり,法定刑には5年以上の有期懲役が定められています。
日本の刑法では,故意に犯罪を犯したのか,故意ではなく結果的に犯罪を犯したのかで成立する犯罪も法定刑も異なるのが通常です。殺人罪と傷害致死罪は結果的に人を死なせたという点では一緒でも,法定刑は全く異なります(傷害致死は3年以上の有期懲役で,無期懲役や死刑はありません)。
これは,故意に犯罪を犯した人の方が責任が重いと考えられているからです。
強盗殺人と強盗致死の特殊性
しかしながら,強盗殺人と強盗致死は死刑又は無期懲役と同じ法定刑が定められています。
殺人罪よりも格段に重い刑が定められているのは,財産目当てで人を襲おうとする者は人の生命を軽視し命を奪う危険性が高いことから,より重い刑で抑止する必要があると考えられているからです。
ただ実際の量刑を見てみると,故意に殺害した強盗殺人と強盗致死では差があります。
被害者1名の事案で見てみると,強盗殺人ではほとんどが無期懲役となるのに対し,強盗致死では無期懲役が減軽され有期懲役となることも多く,強盗致死で無期懲役となるのは悪質な事案です。
強盗殺人罪で刑事裁判で争われること
強盗殺人罪は刑法に規定される罪の中でも最も重い犯罪の1つであり,被害者が1名でも無期懲役,2名以上になると死刑判決になることが多いです。
まず,強盗の意図がいつ生じたかが争いになります。
最初から殺して奪おうと計画し,殺害→物を取るという場合でも,物を取る→殺害という順番でも,いずれでも強盗殺人罪が成立します。
他方で,最初は物を取るつもりはなく,単純に恨みなどから殺害し,殺害したあとに金品奪取の意図が生じた場合,強盗殺人ではなく,窃盗,殺人罪が成立することになり,量刑が大きく異なることになります。
強盗殺人罪では,目撃者等がいることが少なく,いつ財物奪取の意図が生じたのかは,計画性や被告人の犯行前後の行動から推測するしかなく,難しい争点になることが多いです。
また,法定刑は一緒でも故意のあるなしで,強盗殺人か強盗致死かになり,量刑も変わってくることから,殺意の有無も争われることが少なくありません。
強盗殺人になると無期懲役の可能性が高く,現在の無期懲役の実情は,事実上終身刑に近い運用となっており,強盗致死罪となり有期懲役となるかどうかが,熾烈に争われることになります。
強盗殺人,強盗致死と共犯事件
また,強盗殺人や強盗致死事件は,複数の者が共犯関係となって実行されることが多い類型です。
一般的に共犯事件は,首謀者や主犯に重い刑が,従属的な関与の者により軽い刑が科されることになるため,逮捕起訴された者同士で,主従性が問題になることも多くあります。
主従性は,計画段階での関与態様,実際に果たした役割,得た報酬,人的関係等から判断されることになります。もちろん共犯同士に主従はなく,みんなが重い刑となることもあります。
強盗殺人,強盗致死の裁判員裁判
強盗殺人や強盗致死は起訴されると裁判員裁判となります。
重大事件であることから国選であれば2名,場合によって3名以上が選任されることがあります。
そして重大事件であり,犯罪成立上の争点や,共犯者の主従,量刑上の争点など多岐に渡る争いがあるのが通常で,証拠も多くなります。
裁判員裁判は必要的に公判前整理手続に付されますが,公判前整理手続に1年以上かかることも珍しくありません。
公判も,目撃者,共犯者,法医学者など複数の証人尋問が行われることが多いでしょう。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
量刑弁護 執行猶予付き判決の材料を集める
やってしまった行為に対する刑の重さには,再犯可能性が影響します。これ以降は同じような犯罪をしないという説得的な根拠を示すことが,刑を争う事件では1つのポイントになります。特に,懲役刑になるか罰金刑になるか,執行猶予が付くかどうかのような事件では,再犯可能性も無視できない要素です。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
DV事件で逮捕されたら
コロナ禍の下、DV事件は増加している
新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う外出自粛の影響か、家庭内暴力(ドメスティック・バイオレンス。いわゆるDV。)の相談件数が過去最多となっている、とのニュースに触れました。普段は共に自宅で過ごす時間の少ない夫婦や家族が、長時間顔を突き合わせることにより、暴力を振るうといったケースが増加し、顕在化しているようです。
DVはれっきとした刑事事件です。配偶者や親、子に暴力をふるった場合、それだけで暴行罪(刑法208条)に該当します。相手が怪我をした場合、それが打撲や挫創などの比較的軽微な怪我であっても、傷害罪(刑法204条)が成立します。事実に間違いがない場合は、刑罰を受けることになります。
DV事案への捜査機関の取り組みと、勾留のリスク
捜査機関は、伝統的には、「法は家庭に入らず」との考えの下、家庭内暴力の事件で被害者が被害を申告したとしても、捜査に着手することに消極的でした。しかし、近年DVの増加が社会問題化するようになり、現場の弁護士から見ても、警察の対応がより積極的になってきた印象があります。また、継続的に暴力行為が行われ、被害者が何度も警察に被害相談を繰り返していたような場合は、警察も積極的に捜査をする傾向があります。
他方で、事案によっては、夫婦喧嘩の延長に過ぎないようなものもありますし、そもそも一方当事者が被害を過大に申告するか、本来ない暴力被害を訴えるという事案もないわけではありません。このような場合でも、警察が捜査に着手した場合、一方当事者である被害者の言い分を基本的に前提として捜査をすすめますので、冤罪のリスクがあります。
さらに、DV事件では逮捕された後、勾留が相当期間継続する傾向があります。勾留することができる条件の一つに、罪証隠滅をすると疑うに足りる相当な理由があること、というものがありますが、想定されている罪証隠滅行為の典型例が、被疑者に被害者が接触して、被害を取り下げるように圧力をかけたり、供述をかえさせたりする、という行動です。夫と妻、あるいは親と子といった、一定の力関係があり、さらに居住先を同じくしていて容易に接触できる間柄の場合、簡単に上記のような罪証隠滅行為がなされてしまうはずだ、と裁判官は考えるのです。
家庭内でいさかいはあったが、暴力まではふるっていない、それなのに見に覚えのないDV行為で逮捕されてしまったーこのような場合、①いかに勾留をつけさせずに、早期に釈放を勝ち取るか②いかに刑事罰を受けることを避けるか、という点がポイントになります。
いかに早期釈放を勝ち取るか
裁判官に勾留をつけさせないためには、まず被害者と被疑者が容易に接触できない環境を整備し、互いに直接接触しない状況を維持できることを、裁判官にアピールする必要があります。
典型的なケースでは、被疑者が自らの実家に一時的に転居し、刑事事件が終結するまでの間はそこで生活をする、という提案をします。勿論、引っ越し作業等も被疑者家族の協力を得て行い、被疑者が直接被害者と接触することがないように細心の注意を払います。もっとも、単に実家に戻るというだけでは、容易に会ったり電話をしたりすることができる、との理由で勾留がつけられることもありますので、連絡手段についても手当は必要ですし、裁判官によっても判断は大いに分かれるところだと思います。
もう一つのアプローチは、示談交渉になるべく早期に着手するということです。全くの事実無根の場合は、示談等をするのも変ですが、喧嘩や揉み合いにはなったが暴力まではふるっていない、というようなケースの場合、揉み合いになったこと等については謝罪をし、示談をするということもあります。また、DV事件の一部では、被害者も興奮して警察に通報したものの、そこまで大事にするつもりはなく警察に調停してもらう程度のつもりだったのに、予想に反して警察が逮捕してしまい、大事になってしまった、というような経過をたどる事件もあります。このような事件では、被害者と弁護人が早期に連絡をとり、手続について説明し、相互の冷却期間をおくこと等を条件に早期に示談し、また被害届を取り下げてもらう、というアプローチが考えられます。このような交渉が相当程度煮詰まっており、早期の示談成立が見込めるのであれば、勾留がつかないことも十分あります。もっとも、被害者の処罰感情が極めて強い場合や、当方に全く暴力や暴行をした事実はなく、被害者の主張する事実との間に大きな開きがある場合などは、このアプローチは困難です。
冤罪を避けるための公判活動
DV行為があったと検察官が判断し、起訴されてしまった場合、どのように対処すべきでしょうか。実際には暴行をふるっていない、という場合、まさに冤罪の危険にさらされます。公判では、被害者の証言の信用性が一番の争点になります。被害者の証人尋問で、いかに被害者の言い分がおかしいか、弾劾することが必要不可欠となりますし、他の客観的な証拠との矛盾をつくなど、事件全体の証拠を無理なく説明する戦略を立てた上での弁護活動が必要不可欠となります。事件によっては、被害者に生じたとされる怪我の原因を明らかにするため、法医学者などの専門家による鑑定や尋問が必要となる場合もあるかもしれません。
公判で弁護活動が成功し、無罪判決を獲得できるか否かは、弁護人のスキルに大きく左右されます。弊所は徹底的に争う事件を数多く取り扱い、尋問技術や公判での説得技術について研鑽を積んできた弁護士のみが所属しております。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。
公判前整理手続の実態と活用
「公判前整理手続」の実態と活用についてご説明します。

東京・中央区にある東京ディフェンダー法律事務所では、刑事事件のご相談を数多くお受けしています。突然の逮捕や捜査で不安を抱える方の力になれるよう、ひとつひとつの事件に丁寧に向き合ってきました。痴漢や万引き、薬物事件から裁判員裁判の対象となる重大な案件まで、幅広いご依頼に対応しており、これまでに多くの不起訴・無罪の結果を導いてきた経験があります。東京を中心に、関東近郊からのご相談にも対応しています。どんな状況でも、まずはお気軽にご相談ください。